最近、不審な電話が増えていませんか?特に「18」から始まる電話番号からの着信を受けたことがある方は注意が必要です。この番号は、国際電話や特定の通信サービスに関連していることが多く、中には詐欺やスパム電話のリスクも潜んでいます。
本記事では、「18」から始まる電話番号の特徴や、詐欺の手口、そして安全に電話を管理するための対策について詳しく解説します。知らない番号からの着信にどう対応すべきか、ぜひ最後までご覧ください。
18から始まる電話番号の特徴とは?

18から始まる電話番号に関する基本知識
電話番号は、国や地域によってさまざまな形式があり、その先頭の数字には特定の意味があることが多いです。「18」から始まる電話番号については、主にプレミアムサービスや特殊な通信サービスに関連していることが多いと言われています。また、企業のコールセンターやキャンペーン専用の番号として使用されることもあり、特定のサービスに紐づいた番号である可能性が高いです。
日本国内では「18」から始まる電話番号は一般的ではなく、多くの場合、海外の国際電話番号や特定の通信事業者の特殊番号として利用されています。そのため、見慣れない「18」から始まる番号からの着信があった場合は、慎重に対応することが求められます。また、企業のカスタマーサポートや公共サービスが「18」から始まる番号を利用するケースもあるため、一概にすべてが危険というわけではありませんが、事前に発信元を確認することが重要です。
国コード18の国はどこか?
国際電話の国番号は1桁から3桁で設定されていますが、「18」という国コードは公式には存在しません。しかし、国際電話で誤認しやすい番号の一つとして「+1(北米)」や「+81(日本)」に続く番号が「18」となっていることがあります。これにより、詐欺やスパム電話の手口として、海外の番号を装った偽の発信者がこのような番号を使用するケースが報告されています。
また、一部の企業や国際機関が独自に割り当てた特別な番号として「18」から始まる電話番号を使用することがあり、一般的な国際電話とは異なる用途で使われることもあります。そのため、知らない番号からの着信があった場合には、番号を検索して信頼できる発信者かどうかを確認することが大切です。
詐欺やスパム電話の手口として、偽装された国際番号が利用されることがあるため、知らない番号からの着信には十分な注意が必要です。特に、折り返しの通話を要求するメッセージや、高額請求の可能性がある通話に関しては慎重に対応し、安易に発信しないようにしましょう。
電話番号の正しい使い方

電話番号を正しく使うためには、以下の点に注意することが重要です。
- 不審な番号からの着信には出ない。特に「18」から始まる番号や、見覚えのない国際電話は出ないようにし、折り返しもしないことが重要。
- 電話番号を安易に第三者に共有しない。SNSやウェブサイトの登録時に求められる場合は、必須でない限り入力を避け、できるだけプライバシー設定を強化する。
- 国際電話の発信先を確認する。通話料が高額になる可能性があるため、発信前に国番号と相手先をしっかりチェックする。
- 不要なメーリングリストやSMSサービスへの登録を避ける。特に、キャンペーンや懸賞サイトなどで電話番号の入力を求められる場合は、その後のスパムや詐欺のリスクを考慮し、慎重に判断する。
18から始まる電話番号の詐欺の手口

詐欺電話の一般的な手口
「18」から始まる電話番号が悪用されるケースでは、以下のような詐欺の手口が確認されています。
ワン切り詐欺
短時間で着信し、折り返しの通話料金を狙う手口。特に、海外の電話番号を装い、折り返しを促す手法が一般的。折り返すと高額な国際通話料が発生し、通話がつながった瞬間に課金される仕組みが多い。通話時間を長引かせるために自動音声でガイダンスを流す手口も報告されている。
フィッシング詐欺
不審なメッセージや音声案内で個人情報を盗み取る。多くの場合、「あなたのアカウントが不正アクセスされています」「未払い料金があります」などの緊急性を強調するメッセージを送り、個人情報や銀行口座情報を入力させるよう誘導する。近年では、銀行やクレジットカード会社を偽装したフィッシング詐欺が増えており、注意が必要。
国際電話詐欺
高額な通話料金を請求されるケース。詐欺業者が発信元を偽装し、知らない番号からの着信を装ってターゲットに電話をかけさせる。国際電話詐欺では、アフリカや東南アジアの特定の国の番号を悪用するケースが多く、特に「+18」などの不審な番号には注意が必要。
見分けるためのポイント
詐欺電話を見分けるには、次のポイントに注意しましょう。
- 知らない番号からの着信には出ない。特に、「18」から始まる番号や、見覚えのない国際電話には十分な注意が必要です。最近では、AIを活用した自動音声詐欺も増えており、一度でも応答するとターゲットリストに追加される可能性があります。
- 番号をインターネットで検索し、詐欺報告がないか確認することが重要。特に、迷惑電話報告サイトや公式の消費者センターのデータベースを活用すると、危険な番号かどうかを迅速に判断できます。
- 通話料金が高額な可能性がある番号への折り返しは慎重に。特に、海外の電話番号やプレミアム料金が発生する番号(国際有料ダイヤル)に注意し、SMSで折り返しを促されるケースでも安易に対応しないようにしましょう。
詐欺の被害事例
近年、国際電話を装った詐欺の報告が増えています。特に「18」から始まる番号は、国際的な通信網を悪用し、詐欺に利用されることが多くなっています。被害者の多くは、詐欺グループが発信した「ワン切り詐欺」や「フィッシング詐欺」によって、高額な通話料金を請求されたり、個人情報を盗まれたりするケースが報告されています。
例えば、日本国内の消費者が「+18」や類似した国際番号からの着信を受け、折り返した結果、通話料金が数万円以上請求されたケースがあります。これは、悪意のある業者がプレミアム通話料金を設定しており、折り返しの瞬間から課金が発生する仕組みになっているためです。
また、偽のカスタマーサポートを名乗る詐欺も増加しています。たとえば、「あなたの銀行口座に不正アクセスがありました」「クレジットカードの認証が必要です」といったメッセージを送り、指定の番号に電話をかけるよう促す手口が一般的です。このような詐欺では、通話中に個人情報を尋ねられ、パスワードや口座情報を盗み取られるリスクがあります。
さらに、企業や政府機関を装った「フィッシング詐欺」も確認されています。例えば、携帯電話会社や税務署を名乗り、「未払いの料金が発生しています。至急ご連絡ください」といったSMSを送信し、被害者を誘導するケースがあります。詐欺の手口は日々進化しており、一見すると信頼できる組織からの電話に見えるため、十分な注意が必要です。
こうした詐欺の被害を防ぐためには、不審な電話番号には決して折り返さないことが重要です。また、番号をインターネットで検索し、過去の詐欺報告がないか確認することも有効な対策となります。
着信拒否の重要性

電話を受けたときの対応方法
- 知らない番号からの着信には応じない。特に、国際番号や「18」から始まる見覚えのない番号には慎重に対応することが重要です。詐欺や迷惑電話の可能性が高いため、安易に電話を取らずに対応しましょう。
- 留守番電話にメッセージが残されているか確認する。正規の連絡であれば、発信者が要件を残している場合が多いです。メッセージの内容を聞き、不審な点があれば折り返しを避けるのが賢明です。
- 不審な通話内容の場合はすぐに切る。相手が個人情報を尋ねたり、不安を煽るような話をする場合は詐欺の可能性があります。「はい」や「いいえ」といった簡単な返答でも音声データを悪用されるリスクがあるため、無言のまま切るのが最も安全です。
着信拒否の設定方法
スマートフォンには、不審な番号をブロックする機能があります。
iPhone
「設定」→「電話」→「着信拒否と発信者識別」→「迷惑電話を報告」でスパム通話をブロックし、Appleの迷惑電話データベースに追加することで、同じ発信者からの迷惑電話を未然に防ぐ。
Android
「通話アプリ」→「設定」→「迷惑電話をブロック」→「自動通話拒否設定」で、特定の番号や非通知着信を拒否することが可能。また、Googleの「通話フィルター」機能を活用すれば、AIが怪しい電話を検出し、ユーザーが応答する前にフィルタリングを行うため、さらに安全性が向上する。
不審な着信に対する対策
- 着信履歴を確認し、知らない番号はブロックする。特に「18」から始まる番号や、国際電話を装った不審な番号には注意が必要です。スマートフォンの着信履歴から直接ブロック設定を行うことで、同じ番号からの着信を未然に防ぐことができます。また、定期的に着信履歴を見直し、新たな怪しい番号がないか確認すると良いでしょう。
- 迷惑電話の報告サイトを活用し、情報を共有する。オンラインの迷惑電話データベースや消費者庁の情報サイトを利用し、詐欺電話の手口や新たな危険な番号について把握することが大切です。自分が受けた迷惑電話を報告することで、他のユーザーへの注意喚起にもつながります。加えて、SNSやコミュニティサイトで情報を共有することで、より多くの人が詐欺電話のリスクを認識し、対策を講じることができます。
電話番号管理の重要性

SNSと電話番号の関係
最近では、SNSの登録や二段階認証などに電話番号が使用されることが増えています。これにより、アカウントのセキュリティを強化することができますが、一方で個人情報の流出リスクも高まっています。
SNSでは、電話番号を登録することで友人検索が容易になったり、ログインの際に本人確認ができるメリットがあります。しかし、その情報が第三者に流出すると、なりすましやスパム電話、フィッシング詐欺のターゲットになる可能性があります。
また、一部のSNSでは、ユーザーが知らない間に電話番号が公開設定になっていることがあり、個人情報が不特定多数に閲覧される危険性もあります。そのため、SNSのプライバシー設定を見直し、電話番号の公開範囲を適切に管理することが重要です。
さらに、SNSのアカウントが乗っ取られるケースも増えており、その原因の一つに電話番号の流出があります。万が一、アカウントが不正アクセスを受けた場合、登録されている電話番号が攻撃者に悪用される可能性があるため、定期的にパスワードを変更し、信頼できるデバイスでのみログインする習慣を持つことが推奨されます。
このように、SNSでの電話番号の利用は便利である反面、個人情報の流出リスクも伴います。安全に利用するためには、不要なサービスへの電話番号登録を避け、プライバシー設定を適切に管理することが求められます。
電話帳の活用法
- 不審な番号をメモし、次回の着信時に注意する。特に「18」から始まるような不明な番号は、詐欺や迷惑電話の可能性があるため、折り返しを避けるためにも記録しておくことが重要です。迷惑電話対策アプリや電話帳にメモを残し、警戒が必要な番号を明確にしておきましょう。
- 家族や知人の番号は、明確にラベルをつけて登録する。緊急時にすぐに連絡が取れるよう、親族や友人、仕事関係の番号をカテゴリごとに整理すると便利です。また、「自宅」「勤務先」「親友」などのラベルを追加しておくことで、詐欺電話と混同するリスクを軽減できます。
安全な番号管理のためのアプリ
迷惑電話対策アプリを導入することで、不審な着信を自動でブロックすることができます。
- Truecaller:不審な番号をデータベースから自動判別し、リアルタイムで発信者情報を表示。迷惑電話の報告機能が充実しており、他のユーザーと情報を共有できるため、スパム電話の傾向を把握しやすい。また、着信履歴の分析や、特定の番号を自動でブロックする機能も搭載されている。
- Whoscall:スパム通話を事前に警告し、不審な番号の詳細情報を表示。手動でのブロック機能に加えて、迷惑電話の自動拒否設定も可能。さらに、企業や公共機関の公式番号を識別する機能があり、重要な電話を見逃さない工夫がされている。
まとめ
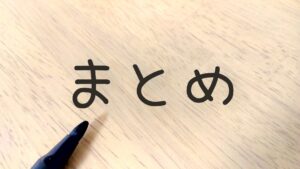
「18」から始まる電話番号は、日本国内ではあまり見られませんが、海外の国際電話や特定の通信サービスに関連している場合があります。特に、詐欺グループが悪用するケースも多く、意図せず被害に遭わないための慎重な対応が求められます。
迷惑電話や詐欺電話から身を守るためには、知らない番号からの着信には安易に応じず、着信拒否の設定や通話ブロック機能を活用することが有効です。また、番号を検索して過去に詐欺の報告があるかを確認する習慣をつけると、より安全な電話管理が可能になります。
さらに、SNSや各種オンラインサービスでの電話番号の使用にも注意が必要です。個人情報が流出すると、スパム電話やフィッシング詐欺の標的になりやすくなるため、登録時のプライバシー設定を見直し、二段階認証を導入することでセキュリティを強化しましょう。
現在、詐欺手口は巧妙化しており、電話やSMSを利用した新たな詐欺が次々と発生しています。日頃から最新の詐欺情報に目を通し、万が一不審な着信があった際は、すぐに適切な対応を取ることで被害を防ぐことができます。


